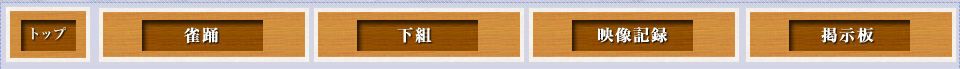下組の雀踊の歴史
雀踊は、今から三百余年前、当下組が当時は土手組と称して水陸の要衝にあたって
殷賑を極めていた頃に、京都より京舞の師匠を薗浦に招き、盆踊りや祭礼等、諸人の
遊楽の際に競って参加し、地方人の無聊を慰め、その後日高地方の各地の祭礼舞踊
として採用され、広まったと伝えられています。
昭和41年9月下組の中に保存会組織「御坊下組の雀踊保存会」を結成し、さらに
組織的な継承を行ない、昭和54年5月御坊市無形民俗文化財指定、続いて昭和56年
7月には和歌山県無形民俗文化財指定をうけ、現在に至っております。
伝承の沿革
下組から小松原へ (今から約180年程前)
「雀踊は宝暦年間(1751~63)存在せし子踊なるものを、今(明治42年)を去る
80年前より変化せし者にて御坊町大字薗小字土手より伝来す。明治42年合祀以後
全然旧来の余興を廃す。」と記されています。
(日高郡湯川村郷土誌草稿の湯川神社の項より参照)
小松原から山野へ (今から約140年程前)
「明治初年湯川町小松原に古くから伝わるものを山野に取り入れたものである。」と
記されています。
(山野区誌より参照)
日高郡内の雀踊
当下組 及び日高川町山野を除き、残念ながらその多くは現在途絶えておりますが、
湯川町丸山におかれては関係者のご尽力により踊りの復活を成し遂げられております。
郡内各地に広まった雀踊の歌詞について、似かよりでグループ分けをすることができます。
| 美浜町吉原 御坊市湯川町丸山 印南町白河 |
歌詞全体が、ほぼ同じ内容です。 |
| 御坊市湯川町小松原 日高川町山野 |
唄い出し前半の歌詞は異なりますが、後半はほぼ同じ内容です。 |
| 御坊市島(春日) 日高町池田 由良町衣奈 |
似かよりがありませんので、全く別の伝承の経路をたどったと思われます。 |
衣装、道具
| 踊り方(踊り連中) | |
| 先奴 | 化粧回し、印をつけた奴襦袢、腰巻、紺と白の角帯、豆しぼり、藺笠、足袋に荒縄巻き |
| 奴 | 印をつけた奴襦袢、腰巻、紺と白の角帯、豆しぼり、藺笠、足袋に荒縄巻き |
| 先奴、奴ともに道具は持ちません。 | |
| 音頭取り (謡方) | 踊り方の奴に同じ、若しくは和装(羽織袴) 道具は扇子 |
| 三味線方 (囃子方) | 踊り方の奴に同じ、成人女性は着物とおけさ笠 道具は太棹三味線 (女性は細棹も可) |
 先代(左)より譲受した化粧回しを披露する新先奴 |
 囃子方の衣装(成人女性) |
 奉納時の様子(謡方と囃子方) |
|
奉納
小竹八幡神社の秋季例大祭(放生会)にて奉納 (10月5日午後1時過ぎ頃)
雀踊の奉納を行なう踊り連中、謡方、囃子方等の人員は、祭礼に於いて下組の
大道具、獅子舞、幟等に加わる若衆を割いた上で人員を募るために、必然的に
主として役員以上のメンバーとなりますが、最近は可愛らしい幼稚園、小中学生や
女性の参加希望者も増え、年々賑やかな奉納に変わりつつあります。
奉納の形は、中央に謡方と囃子方が輪になり配置、その周りを踊り連中の輪で囲み、
右回りに進みながら踊ります。
当祭礼は、時期的に雨になることも多く、囃子方と謡方の衣装・道具が濡れない様、
雨の対策をして踊りの輪の外で演奏し唄って奉納する事が習慣化していました。
今後はそれを改め、よほどの雨でない限り本来の形である踊りの輪の中に鳴り物を
配置する事としています。
 唄い出し雀の所作 |
 雀の所作 |
 当世よーいよーい |
 手踊り「千鳥」の反転部 |
 四季の「秋」の紅葉踏み分け |
 四季の跳ね踊り所作 |
雀踊の詞章
詞章は「めでたのや」と祝ぎ言(ほぎごと)から始まり、続いて権中納言敦忠、侍賢門院
堀河、小野小町等の詠んだ歌などを引用した艶冶な恋歌となり、一転して四季それぞれの
花鳥風月と風情を詠んだ古人の歌を引用し、美辞を連ねて行楽のさまに物事の裏表を
唄いあげながらも、楽しみはその中にあるとして、この地小竹の宮で浮かて踊れば、神も
慰み民も安全となる。と唄い上げて踊る奴踊り形式の典型をとっています。
| 踊り方の掛け声 「トーセーヨーイヨーイ」 ・ 「ヨーイヨーイ」 「ハ ガーテンジャー ヨーイヨーイ」 「ハ ソーコーデーセー ヨーイヨーイ」 「ハリショ ヨイショ サッサノヤー」 「ドッコイ」 ・ 「ソラドッコイ」 「エードッコイ」 ・ 「ハーヤ」 「コラショ」 ・ 「イヤ」 |
三味線方の合いの手 「ヨオイ」 ・ 「イヤ」 |
| 音頭取りの掛け声 「ヨーオ」 |
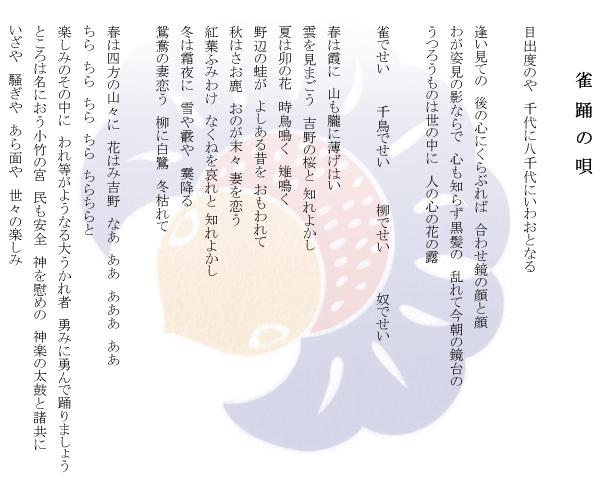
茶免
江戸時代の御坊の薗浦に○○免という地名が七つあり、七免と呼ばれていたそうです。
茶免、堂免、烏免、白免、公役免、・・・等。
その昔、領主より免税されていた名残といわれていますが、唯一茶免だけが現在も
正式な地名として残っています。
当地の庄屋が上役人にお茶をもてなして話し合いをし、税を免ぜられたとの説が
言い伝えられています。
茶免延命地蔵尊
元は日高川沿いにあった地蔵尊を明治22年の水害後に茶免に移し祀られているものだとか。
古くから「茶免のお地蔵さん」と呼ばれ、今でも地元の人々から信仰を集めています。
この祠の側に浄瑠璃の名手といわれている「紀国太夫事 豊竹君太夫」と、三味線の名手と
いわれた「豊沢広七 碑」の二つの石碑があります。
「地蔵尊」と二人の石碑には特に関連性はないとの事ですが、この石碑が雀踊の茶免に
あることから、「雀踊」とは何らかの関連がありそうです。しかし現在のところそのことは
明らかになっておりません。
平成24年 下川河川改修に伴い地蔵尊は約100m南に移転しました。
 移転前の旧茶免地蔵尊 |
 二つの石碑 |
 移転後の新茶免地蔵尊 |